平成28年春号(vol.41)
 |
 |
 |
|---|---|---|
| 鳳鳴大滝 | ||
 |
| 平成28年ボランティア活動予定 | |
|
みやぎ会では、東北地方整備局が行っている「ボランティア・サポート・プログラム」の認定を受け、国道48号の清掃活動を行っています。 活動は4~11月の第4土曜日で、平成28年の活動は下記の日程で宮城総合支所駐車場に集合し、午前6時半から約1時間程度の作業をう予定です。
|
 
|
平成21年春号から『会員の広場』というコーナーを設けましたので、会員のあなた様の”常々思っていること”、”あなたの周りのあんな事、こんな事”等掲載をしていきたいと思いますので、是非ご愛読よろしくお願いします。
目次
3.田子倉ダム(平成28年夏号(vol.42)掲載)
4.奥只見ダム(平成28年秋号(vol.43)掲載)
5.只見線物語(平成28年冬号(vol.44)掲載)
6.おわりに(平成28年冬号(vol.44)掲載)
1.只見川
「只見川」という川の名前は知っていても、水系や合流する河川についてはその川の所在位置などを明確にできないかもしれません。改めて地図を眺めてみると、川筋は尾瀬ヶ原を水源に持ち、阿賀川(福島県)に合流し、名を変えて阿賀野川(新潟県)として日本海に注いでいます。阿賀川や阿賀野川、尾瀬ヶ原のことはわかりますが、次のことは知りませんでした。尾瀬ヶ原は群馬県ですが、そこから流れ出る只見川は右岸側が福島県、左岸側が新潟県となっており、奥只見ダムはまさに県境に建設されています。奥只見ダムを下ると、福島県に入り、田子倉ダム、只見ダムなどがあります。
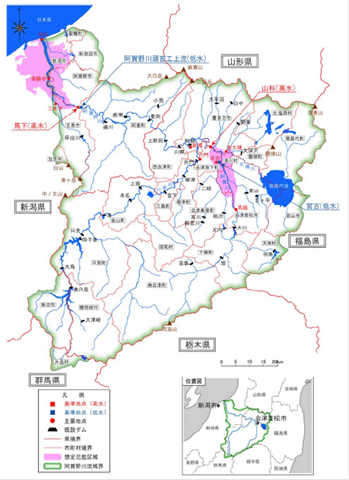
【 図-1 阿賀野川水系図 】
市町村名でいうと、右岸側は檜枝岐村、只見町、左岸側は魚沼市となっています。JR線の只見線は魚沼市の小出から会津若松を結ぶ路線ですが、奥只見ダム周辺は通らず、田子倉ダム近傍を通ります。道路は只見線沿いに国道252号があり、奥只見ダム方面は新潟から福島へ抜ける国道352号から県道を経て行くことになります。
只見川開発については、Wikipediaをみると大凡の経緯がわかり、田子倉ダム、奥只見ダムについても事情が理解できます。戦後の復興、高度成長期の発展を支えたエネルギー開発事業の一つとして著名ですが、一方で様々な問題が発生したことが記されています。調べて見ればいろいろ興味深い事柄が発掘できまです。同じく、この時代に建設された黒部ダムと比較すると、同様の厳しい自然環境のもとでのダム事業でありながら、人間社会を色濃く映し出した事業であることが推測できます。
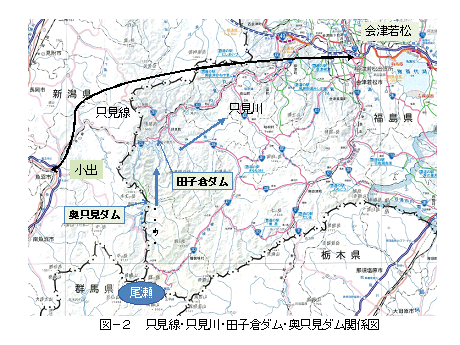
【 図-2 只見線・只見川・田子倉ダム・奥只見ダム関係図 】
只見川が群馬県に水源をもち、新潟・福島の両県を流れ下る川であったため、総合開発計画をめぐり、両県間に利害抗争がありました。特に新潟県側の強烈な分流案提示意見が出されたり、昭和の初期に只見川筋の水利権を獲得した東京電力と東北電力の確執、福島県の訴訟問題、最終計画案で決まった電源開発(株)の事業進出などかなりもつれた事情があるようです。
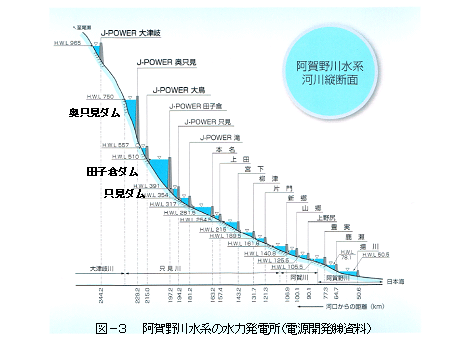
【 図-3 阿賀野川水系の水力発電所(電源開発(株)資料) 】
両ダムとも水没者がいて、その補償問題で物議を醸し出していました。田子倉ダムでは共産党に支援された激しいダム建設反対活動が起こったため、福島県知事の斡旋を受けて事業者側が破格の補償金提示したこともあり、田子倉ダム補償事件として歴史に記録されています。
奥只見ダムの「奥只見」という名称ですが、只見川開発計画の目玉地点の名としてふさわしいものが検討され、当初の地名由来の「須原口」発電所を改めて「奥只見」と命名されたとのことです。その後全国各所の発電計画に「奥」の字がつく地点がでてきますが、奥只見をもって嚆矢とするということです。
2.二つのダム
田子倉ダム、奥只見ダムともダムの分野では著名なダムです。
奥只見ダムは建設当時は日本で堤高、総貯水量とも1番のダムでした。堤高は3年後に黒部ダムに、総貯水量は8年ほど前に徳山ダムに1位の座を譲っています。
二つのダムのダム・発電所の諸元を表-1に示します。
(電源開発(株)東日本支店小出電力所パンフレットより作成)
表-1 ダム・発電所諸元
| 田子倉 | 奥只見 | ||
| 型式 | 重力式コンクリートダム | 重力式コンクリートダム | |
| 堤高 | 145m | 157m | |
| 堤頂長 | 462m | 480m | |
| 堤体積 | 195万立法メートル | 164万立方メートル | |
| 総貯水量 | 49,400万立法メートル | 6,100万立方メートル | |
| 流域面積 | 816.3平方キロメートル | 595.1平方キロメートル | |
| 湛水面積 | 9.95平方キロメートル | 11.5平方キロメートル | |
| 溝水位標高 | 510m | 750m | |
| 発電所 | 田子倉 | 奥只見 | 維持流量 |
| 形式 | ダム式 | ダム水踏式 | ダム式 |
| 最大出力 | 40万KW | 56万KW | 2,700KW |
| 最大使用水量 | 450立方メートル/秒 | 387立方メートル/秒 | 2.56立方メートル/秒 |
| 最大有効落差 | 105m | 170m | 130.3m |
| 水車形式 | 立軸フランシス水車 (1台) | 立軸フランシス水車 (4台) | 横軸フランシス水車 (1台) |
最近では、真保裕一の小説「ホワイトアウト」とその映画(2000年上映)の舞台となったダムとしても有名になりました。小説の舞台は奥只見ダム(小説では奥遠和ダム)ですが、撮影では黒部ダムや田子倉ダムが使われたとのことです。私も映画を観ましたが、主人公がダムを占拠したテロリスト集団と一人で闘うダイハード張りのアクションものです。テロリストや外国からダムが破壊攻撃を受けたらどうするか、などの話題性はありました。
主として撮影は黒部ダムで行われたということです。映画監督が黒部ダムのようなアーチダムの現場を作品のイメージにしたかったからのようです。元玉川ダム所長のH氏から、映画ではだめだ、小説を読まなくてはいけない、と意見されたほか、この小説の巻末に参考文献として水源地環境整備センターで出版している図書が記載されていることに感激したとも話され、よく勉強していると賞賛されています。
一方で、有名な作家も二つのダムを舞台にして、土木技術者・ダム技術者を主人公に小説を書いています。
土木学会でもおなじみの曾野綾子は田子倉ダムを舞台に「無名?」を昭和44年に発表しています。学生時代に読みましたが、口さがない友人達はハイダムもやり、高速道路も何でもやるなんて、そんな土木技術者はいないし、現実的ではないと冷ややかに批評していたのを思い出します。土木技術者を主人公にするなどあまり事例もなく、「黒部の太陽」よりは色恋など人間模様も入り、まさに青春小説という印象を持ちました。その後、曾野綾子氏の一貫した土木や土木技術者を応援してくれる姿勢には敬服します。東京電力が建設した高瀬ダムを舞台にした「湖水誕生」も同じようにダム技術者が主人公ですが、電力技術者であり、電力開発側からの視点に描かれていますので、河川協議の相手である建設省に関する描写は揶揄された表現振りです。いずれの小説も、現場で働く、民間施工会社や民間会社の取材をもとにつくられているからかもしれません。
城山三郎は「黄金郷」という作品を書いています。50年以上も前に発表された作品で、あまり世に知られていなかったらしいのですが、平成22年(2010年)に講談社文庫として再刊されました。私も作品の存在は知っていたのですが、未読でしたので早速入手しました。主人公はダム事業者側の現場事務所の若い社員です。用地買収に水没地域を奔走するダム建設所長と地元地権者のやりとりが描かれています。「黄金」というのは、水没地の石や木などなんでも金額が付けられ、俄成金になった地権者たちを象徴しています。4戸の家族が最後までダム建設反対の立場で残りました。ようやく移転交渉が妥結したのも束の間、初冬の降雪時、ダム水没地の狭い道路を走行中、運転を誤ってダム補償費で購入した外車もろとも谷底へ転落するという悲劇を終盤に迎えます。
文庫発売当時は、折しも、民主党政権の発足時でした。早速、M国土交通大臣が現地の声も聞かずにマニフェストに書いてあるからと八ッ場ダム建設中止を高らかに宣言したことを取り上げ、民主党議員にこの小説を読ませてダムの現場の実情を理解させるように、もっと早く、文庫版を出版してもらったらよかった、と江上剛は解説で述べています。全く同感です。
田子倉ダム補償事件について関係資料(文献(8)(9))から引用してみます。
田子倉ダムにより水没する田子倉部落には50世帯、280(290)人が住んでおり、約48町歩の耕作地と1270町歩を超す共有林がありました。林業が盛んで、山菜、魚、自家用薪炭など自由に取れたことなどから1戸当たりの所得は福島県平均を上回っていたそうです。この地域に対する住民の愛着もひときわ強かったことも加わり、激しい反対運動が起こったため、水没補償問題はその解決までに時間を要しています。
昭和28年の補償交渉開始当時、地元は総額35億円の補償を要求しましたが、翌年決裂しました。電源開発が提示した補償案では住民との交渉が暗礁に乗り上げたことから、福島県知事が仲裁に入り、独自の斡旋案を提示し、住民(50戸の内30戸)と電源開発が合意し、調印が行われました。この内容は住民側の意見に沿ったものが多く、内容も補償額も過去のダムに比べ高額となっています。しかし、この合意案を巡って問題が大きくなりました。通産省や建設省が今後の公共事業の執行に多大の影響を及ぼすことを理由に反対します。電源開発本社も所長が了承したものであって、総裁が了承したものではないとして、新たに補償推進本部を組織のうえ補償問題を解決する方針に変更しました。
結局、中央省庁主導、電源開発本社主導で補償交渉は進められ、半年後、補償案が提示されて福島県知事案より多い45戸が受諾することになり、交渉が妥結しています(昭和30年)。残る5戸も翌年に妥結し、用地交渉は完了しました。
斡旋案は総額約9億2千万円、これに反対した通産省は約半分の4億9千万円にすべきと主張したようですが、最後は6億3500万円となりました。広大な山林の取り扱いが大きく異なり、斡旋案は水没以外の共有林も一連で補償するものでしたが、通産省、電源開発案では水没区域のみで残地の補償はしないとするものです。これだけでも2億数千万円の減額になるものでした。水没しない山林を所有していたところで移住後の生活にはほとんど役に立たないので、山林全体を買い上げてくれというのが地元の要求だったようです。
実際には、電源開発は貯水池の奥地の村有林に対する補償との名目で2億8500万円を支払い、このうち、4460万円を村に、2億4000万円を水没者に支払っています。実質的な補償額は知事斡旋案どおりの9億2千万円になったということです。華山謙は、只見川電源開発を巡って新潟県と対立抗争があった福島県が面子をかけて早急に補償問題を解決する必要があったこと、電源開発にとっても政争のいきがかり上同意せざるを得なかったことに加え、発電事業の経済効率が良かったので多少補償費が高くても田子倉ダムを早く完成させるほうが得策だったためと分析しています。
これら一連の顛末の様子は城山三郎の小説にも描かれています。
奥只見ダムでは、あの三島由紀夫が若い頃「沈める滝」(昭和30年)という小説を書いています。ニヒルなダム技術者が主人公として登場し、恋愛関係にあった人妻が只見川に入水自殺を図って終わる、という話です。最近読みました。小説では奥野川ダムとなっており、ダムに関する描写は曾野綾子ほどの土木技術に対する突っ込みは感じられません。漫才家で芥川賞をとった又吉直樹の作品「火花」と同様に、この小説は最後の結末に疑問符がつきそうで、これは何だろうという読後感が強く残ります。しかし、感性豊かな作家のダム即ち人造物に対する所感が主人公を通して語られています。
三島由起夫の小説から引用してみます。
『技術が完全に機械化される時代が来れば、人間の情熱は根絶やしにされ、精力は無用のものになるだろうから、科学技術の進歩にそそがれる情熱や精力は、かかる自己否定的な側面を持っている。しかし幸いにして、事態はまだそこまでは来ていない。
ダム建設はこのような意味で、一種の象徴的な事業だと思われた。われわれが山や川の、自然のなお未開拓な効用をうけとる。今日ではまだ幸いに、われわれ自身の人間的能力である情熱や精力の発揮の代償としてうけとるのだ。自然の効用が発揮しつくされ、地球が滓まで利用されて荒廃の極に達するまでは、人間の情熱や精力は根絶やしにはされまいという確信が昇にはあった。
ダム建設の技術は、自然と人間との戦いであると共に対話でもあり、自然の未知の効用を掘り出すためにおのれの未知の人間的能力を自覚する一種の自己発見でなければならなかった。』(平成28年夏号(vol.42)へ続く)
- (参考文献)
- 1.只見川
- (1)Wikipedia 田子倉ダム及び奥只見ダム
- (2)只見川水力開発の想い出 北松友義 No.189電力土木 59.3
- (3)只見川電源開発計画について 市浦繁 発電水力No.5
- (4)只見川踏査記 後藤荘介 No.154電力土木 53.5
- 2.二つのダム
- (5)ホワイトアウト 真保裕一 新潮文庫
- (6)無名碑 曾野綾子 講談社
- (7)黄金郷 城山三郎 講談社文庫
- (8)補償の理論と現実 p53~56 華山謙 勁草書房
- (9)復興期における只見川電源帰属問題と東北開発(上)(中)(下)仁昌寺正一
- 東北学院大学論集 経済学 (123), p51-107, 1993-09(124), p81-114,
- 1993-12(128), p61-97, 1995-03 東北学院大学学術研究会
- (10)沈める滝 三島由紀夫 新潮文庫
- (出典)
- 1.只見川
- 図-1 阿賀野川水系図:国交省HP http://www.mlit.go.jp/river
- 図-2 只見線・只見川・田子倉ダム・奥只見ダム関係図:平成26年度版管内図東北地方整備局(http://www.thr.mlit.go.jp/)を加工
- 図-3 阿賀野川水系の水力発電所(電源開発(株)資料):電源開発(株)東日本支店小出電力所パンフレットを加工
記 島田 昭一
先日届いた「東北建友会報 第114号」一声運動を拝見すると皆さん病のこと、孫のことのお話はなく大半の方は趣味のこと、運動・健康増進のことなど楽しく余生を送られている様子がうかがわれうらやましく読ませていただきました。
私は相も変わらずの体調で何とか過ごしております、昨年の観桜会の頃外孫ですが待望の男の子が誕生し位牌持ちを授かりました、その孫も間もなく誕生を迎えます体重も10Kg近くあります、近くに住んでいるので保育所に行くまでの間我が家で爺・婆が保育の手伝をしています。ハイハイをしはじめたころから部屋中を追い掛け回しているうちに爺・婆共に腰を悪くしたが何とか誕生日を迎えられそうです。蛇足ですが初めの孫(外孫)は既に社会人となり東京に就職し頑張っております、婆さんは手作りの料理を宅配便で送るのを楽しみにせっせと孫孝行をしています。
年とともに最近身にしみて感じることがあります、高齢に伴う身体の不自由さと地域社会(隣近所)とのつながり方です、特に体調が思わしくない状態での冬季の雪寄せに毎年悩んでいます。7年ほど前に雪寄せ中に雪に覆われ隠れていた氷に足を取られ横転して息もできない状態で病院に駆け込み肋骨が折れているとのことで手当てを受け、二日後に受診したら肋骨が4本折れていると云うことでギブス充てられ一か月程自宅療養を余儀なくされたことがありました。そんな状況に加え、ここ毎年2~3回はどか雪が降り雪寄せの苦労です、私は体調が思わしくなく体重37Kgの妻に任せきりで妻も家の周りの雪寄せで精一杯で道路まではなかなか難しいところです。
拙宅は市道(幅員5~6m)と私道(幅員6m、延長95m、行き止まり)の角地に位置し,私道には10軒の住居が張り付いている、市道は積雪10㎝で除雪することになっているが、ここ4、5年は除雪車が来たことはないように記憶している。問題は私道のほうです、高齢の進む中奥の方々をはじめ皆さん早朝から雪寄せに頑張って中には市道まで人幅の雪寄せをする方もおられます、私道の入り口にあたる拙宅が雪寄せをサボルと向かいのご夫婦が拙宅の事情見かねて当方の側まで雪寄せをしてくれています。その雪寄せの音を聞くと申し訳なく身の細る思いで過ごしております、後でお礼の言葉で勘弁していただいて居るところです。この10軒のブロックは4~5年で80歳(ご主人)を超えるお宅が6割を超えると思われます、超・超高齢化の地区です、現実、市道のとなりの家、向かいの家が空き家(施設に入所)、他に知る限りでは2軒の空き家が近所にあります。2007年に超高齢社会になった頃第二の職場を退職し年金生活に入ったが、先の会報で「健康寿命」を拝読して長寿が良いのかどうか悩んでいる今日この頃です。つじつまの合わないことを書いて字数を稼いで駄文としました。
2011年の大震災の犠牲者のご冥福をお祈り申し上げます。
記 田口 陸男
平成18年4月に開設された「みやぎ会ホ―ムページ」は、平成28年冬号で標記を達成し、1月30日に祝賀会が開かれました。
当日は、開設当時の菅原会長、現清水会長をはじめ会報に関わる皆さんに参加いただきました。
及川編集委員長の進行で、発足当時の中心メンバー平野さん、投稿数ダントツ1位の高橋成美さん、編集で最もお世話になっている協会の瀬尾さん等々にもふれられ、差し入れの日本酒で和気あいあい賑やかに盛り上がりました。
年にきっちり4回の会報を続けてきた及川編集委員長はじめ編集委員の皆さん、今後どこまで続けられるか、まずは10周年ご苦労さまでした。
(報告者 田尻)
編集委員会では、会員の皆様からの原稿を募集しています。
おもしろい話、地域の出来事等、ドシドシ、お寄せ下さい。まってまーーーす。
【問い合わせ先】
担当:及川 公一郎