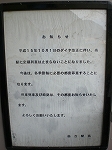| 平成20年秋号(vol.11) | ||
 |
 |
 |
|---|---|---|
| 鳳鳴大滝 | ||
| 平成20年ボランティア活動状況 | |
|
みやぎ会では、東北地方整備局が行っている「ボランティア・サポート・プログラム」の認定を受け、国道48号の清掃活動を行っています。なお、この活動につきましては東北建設協会の「みちのく国づくり支援事業」に採択され、傷害保険の支援を頂いております。 |
  |
今回は吉成地区です。仙台市の中心部から北西に位置し、市内から見ると仙台大観音様が見えるので良く分かります。大観音の左側の小高い山を中心に斜面が団地となっています。仙台駅(旧市街地)からの道路と八乙女〜折立を結ぶ北環状線が中心の道路となって住宅地が連なっています。古くは吉成山一帯は伊達藩のお狩場であり、仙台市の紋所に因んだ三矢の矢柄となっている矢竹等が生繁っていたと記されています。近年では、旧仙台市、旧泉市、旧宮城町、の境界が仙台大観音の傍で現在も青葉区と泉区の境界となっています。私の住んでいる団地は元の字名は吉成山と言い煉瓦用の土の土取場だった様でそれを開発して団地としたので開発業者の名称(伊勢産業)から伊勢吉成団地と呼ばれたもので昭和55年に吉成山から吉成丁目に変更しております。現在は旧市街地のベットタウンとして大規模スーパー、飲食店、家電量販店が進出し、市街地として賑わっています。
私が家を建てた昭和59年頃は国見ヶ丘、南吉成団地も無く、山の中の小さな団地で落ち葉等が吹き溜まりとなっていて 活用して菊造り等をしましたが、今では一部を残して住宅地となっています。標高200M〜250Mで旧市街地より150M程高いことから夏は気温が2,3度低く、冬は当地が薄っすらと雪で白くなっても旧市街地に下りると雪が全然無い等若干の気温差があります。また、晴れた日は遠く蔵王連峰が見え、市街地の方は高層ビル街、その奥は仙台平野、塩釜港、仙台湾、太平洋と風光明媚な団地であります。
仙台駅まで約7KMと歩くと1時間40分程です通勤は一般的にはバスですが、JRの国見駅まで歩いて25分位ですが 帰りは上り坂道で30分以上かかります。仙台駅までは自転車で一部登りが有りますが殆んど下り坂で無動力でブレーキのみでいけます。海を見ながら当団地に寄ってけさいん。
吉成地区周辺の世帯数、人口
| 地 区 | 世 帯 | 人 口 |
| 吉成台1〜2丁目 | 211 | 666 |
| 吉成 1〜3丁目 | 1,058 | 2,651 |
| 南吉成1〜7丁目 | 1,373 | 3,695 |
| 国見ヶ丘1〜7丁目 | 2,243 | 5,999 |
| 計 | 4,885 | 13,011 |
平成20年4月1日現在 仙台市調べ
記:高橋 成美
「仙山線」シリーズ今回は「西仙台ハイランド駅」についてご紹介いたします。
今回は、仙山線の熊ヶ根駅と作並駅の間にある非常に珍しい駅を紹介します。それは「西仙台ハイランド駅」という臨時駅で、仙山線に2つある臨時駅のひとつです。
5年前から、この駅に停車する電車はまったくありませんので、本当に駅といっていいのか疑問もありますが、JR東日本のホームページや時刻表にも掲載されていますので駅であることには間違いありません。
国道48号沿いにありますので、この駅の存在はもちろん知っていましたが、私自身利用したことはありません。今回、この記事を作成するに当たり、初めて駅に行ってみましたが、ホームは立派に残っていて、今でも駅としての最低限の機能は維持されているのではないかと思いました。ちなみにこの駅は、国道48号を山形方向に向かって走り、熊ヶ根を過ぎて仙台ハイランド入口交差点の右側にあるのですが、注意しなければ、そこに駅があるとは気づかないかも知れません。
この駅は、民間会社の「(株)青葉ゴルフ西仙台ハイランド(当時)」が、当時の国鉄に要望して同社が費用を全額負担して設置した請願駅で、1987年(昭和62年)3月21日に臨時駅として開設されました。
「西仙台ハイランド」(1990.8「仙台ハイランドに改称」)は、1973年、当時の宮城町新川(合併により仙台市青葉区)にゴルフ場を開設し、その後スポーツ公園、遊園地などを開園し、1986年にはサーキットをオープンした総合レジャー施設です。
サーキットの開設により、レース開催時には全国からファンが集まり国道48号が渋滞したそうです。そのため、電車利用の利便性を高めて電車での来場を促すべく請願駅の設置に至ったそうです。駅からサーキット場までは約3kmと遠いため、来場するお客様は駅から無料で送迎することとしました。
当時は、土・日曜、春休み・夏休み期間及びゴールデンウィ−クなどに快速以外の一部の電車が停車するほか、同施設でのイベント開催時に臨時列車の運行などがあったそうです。
しかし、レースに来場するファンの自動車利用はあまり減らず、また、普通電車しか停車しない当駅を利用するよりも、快速電車が停まる作並駅から送迎してもらった方が、お客さんにとっては利便性が高いことなどもあって、当駅を利用するお客さんは思いのほか伸びなかったようです。ちなみに、2002年当時のダイヤによると、土・日の7〜15時台に上下各8本が臨時停車されていた記録があります。
2003年10月1日のダイヤ改正により電車の停車がなくなり、現在は熊ヶ根駅及び作並駅からの無料送迎を行っていて、芋煮会などで来場するお客さんの作並駅からの送迎要望があるとのことです。JR東日本及び「仙台ハイランド」を取材した感触から、この駅の再開はないのではないかと思いました。
(記 森山 清治)
東北の霊場「定義如来」
庶民に「定義さん」として親しまれている東北の霊場「定義如来・西方寺」は、仙台市街、国道48号線熊ヶ根分岐点より北へ向い、仙台の水がめ「大倉ダム」の湖面を眺めながらさらに車で走ること約10分、途中の風景とは一変した豊かな自然に囲まれた地にあります。
今から約300年前に開山した「定義如来・西方寺」には、新本堂のほか貞能堂と呼ばれる旧本堂や五重塔、子育て観音、展示室、茶室などがあります。
縁結びや安産の神様として名高く、お詣りすれば一生に一度は必ず祈願が叶うと言われており、若い人達から家族連れやお年寄りまで、幅広い参拝客等で年中賑わいを見せています。
■ 「定義如来」名の由縁
平安末期、壇ノ浦の戦いに敗れた平氏の重臣・平貞能公が、中国(欣山寺)より平家に送献された宝軸「阿弥陀如来の画像」を守り、源氏の追討から逃れるためこの地に隠れ住み「地名」も「定義」と改め、建久9年(1198年)7月7日、御年60歳で亡くなるまで、ここで暮らしたと言い伝えられています。それが「定義如来」名の由縁です。
■ 貞能堂(旧本堂)
貞能公の遺言により建てられたという、貞能堂と呼ばれる「旧本堂」の墓には宝軸「阿弥陀如来の画像」が安置されていると言われています。
境内には鐘楼があり、旧暦の大晦日には除夜の鐘が鳴り響くそうです。
■ 天皇塚「連理の欅(けやき)」
文献によれば、この塚には安徳天皇の遺品が埋められ、その墓標として2本の欅が植えられたそうです。やがて、その欅が1本の木として結ばれたことから「連理の欅」と呼ばれるようになった・・と言い伝えられています。
この欅は、縁結びの神木としてご利益があると言われております。このことから、多くの若い人達の信仰を集めており、今ではデートコースにも入っているとのことです。
■「定義名物」のおすすめ
三角あぶらげ・・・・分厚い揚げたてのアツアツに醤油と七味唐辛子をかけて思いっきりがぶり付く。意外とあっさりして、ビールのつまみには最高。
休日等はひっきりなしに訪れる参拝客等で行列をなしている人気スポット。
やきめし・・・・おにぎりに秘伝の味噌をタップリ塗り、炭火で焼き上げたもので、ボリュームが満点で香ばしく美味。
他にも、玉コン、みそ田楽、焼きダンゴ、定義まんじゅう等。
今、「定義如来・西方寺」は仙台近郊でも指折りの観光名所になっています。参拝客等が行き交う門前町には、旅館や土産品などの店が建ち並び年中を通し参拝客が絶えることがなくいつも賑やかです。また定義の地は豊かな自然に囲まれ、四季の移り変わりが素晴らしく、特に紅葉の時期は圧巻です。
一度ゆっくりお詣りされ定義の豊かな自然を満喫されて見ては如何でしょうか。
( 記:藤田守雄 )
宇宙を身近に。
- 誰もが本物の宇宙と出会える「眼」になります。
- くらしの中に宇宙を見つける、体験と情報を届けます。
- 市民がつくり、市民がふれあう。一人ひとりが主役の天文台へ
をめざして、青葉区錦ヶ丘に仙台市天文台が西公園から移転・開館したので、見学に行ってきました。
国道48号愛子バイパスから錦ヶ丘団地に入り、仙台ヒルサイドアウトレット手前の交差点を右折し、県道132号秋保温泉愛子線を約700m進んだところの右側にありました。
天文台によく見られるドーム型の屋根がないので、え?これが天文台!と思われるような建物でした。
125台収容の駐車場に車を置き、建物を1/4周した所の入館口から中にはいるとオープンスペースがあります。ここは、全てのゾーンへの入り口となる交流広場です。
奥に観覧料を支払う受付があります。観覧料は表の通りです。
観覧料
| 一 般 | 高 校 生 | 小中学生 | |
| 展示室 | 600 | 350 | 250 |
| プラネタリウム | 600 | 350 | 250 |
| セット券( 展示室+プラネタリウム ) | 1,000 | 600 | 400 |
| 年間パスポート | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
単位:円
私が行った時は、開館1ヶ月後くらいの午後でしたが、プラネタリウムは人気があり午前中で券が売り切れ、見ることは出来ませんでした。
施設案内
1階には、オープンスペースを中心にプラネタリウムゾーン、展示ゾーン、活動ゾーン、天文ライブラリー等があります。
・ 展示ゾーン
見て、触って、宇宙のスケールを体感!
大きな太陽系模型やCG映像などで驚きと感動にあふれた天文の世界を直感的に楽しく探求できるゾーンです。「地球」「太陽系」「大宇宙」「天文学の歴史」の4つのエリアに分かれており、展示物を活用したミニワークショップなども開催予定。
・ プラネタリウムゾーン
直径25mの水平型ドーム、座席は280席。これまでの「光学式プラネタリウム」に「デジタル式プラネタリウム」を融合させたハイブリッドシステムで、様々な星座を見ることが出来、宇宙の魅力を体感できます。
また、9月10月のスケジュールとして星空ライブとして「『かぐや』、月へ行く」、「日本の惑星研究最前線」、シアターとして「スターオブファラオ」、「シークレット・オブ・ザ・サン」、ファミリー向けとして「仮面ライダーキバ&電王〜デンライナー宇宙へ!〜」、「プラネくんとあそぼう!」、ミュージックとして「70's洋楽コレクション」、「宇多田ヒカル特集」等を行っています。特にファミリーではお子様(小学校低学年以下)向けの上映を土曜、日曜の11:30から行ってますので、ぜひ出かけてみて下さい。
・ 活動ゾーン
仙台市天文台の基礎を築いた、初代台長加藤愛雄博士と二代目台長小坂由須人博士の功績をたたえてつくられた大ホール。
企画展や講演会、ワークショップなどのさまざまなイベントを開催します。
・ 天文ライブラリー
天文関係の雑誌や本を取り揃えています。
宇宙や天文について知りたいことは、ここでじっくり調べることができます。
フリースペースです。
2階は、学習室、資料室、天体ギャラリー等が、あります。
3階は、観測ゾーンです。
・ 観測ゾーン
観測デッキ、1.3m望遠鏡観測室、太陽望遠鏡観測室等があります。
■ 1.3m望遠鏡観測室
公開天文台の中では、国内3番目の大きさを誇る口径1.3mの大型望遠鏡。
17等星ほどの暗い星まで観測可能で、観測研究はもちろんのこと、毎週土曜日の夜には、一般向けの天体観望会も開催します。
レンズは口径1.3mともなると国内では研磨は出来ないので、ロシアのサンクトペテルブルグ市内の業者が行い、京都の望遠鏡メーカーによって組み立てられました。
望遠鏡の操作は、タッチパネルを装備、参加者が見たい天体をタッチすると、望遠鏡が自動的に動き出し天体が視野内に導入されます。
性能は、直径38mmのピンポン球が70km先に離しても見えます。また、肉眼で約6,000個の星を数えることが出来ますが、1.3mにもなると3億5000万個も数えることが出来ます。値段は3億円だそうです。
■ 惑星広場
観測棟を太陽に見立て、太陽系の惑星軌道(水星〜木星まで)を75億分の1のスケールでデザインした市民の憩いの広場。散歩やランチタイムを楽しみながら、太陽系の大きさを実感できます。
■ 移動天文車「ベガ号」- あなたの街に星をお届け
毎週金曜日の夜に、市内の学校や市民センター、勾当台公園などに移動天文車「ベガ号」と天文台スタッフを派遣して、天体観望会を実施しています。
利用案内
| 開館時間: | 9:00 〜 17:00( 土曜日は21:30まで ) |
| 休館日: | 月曜日、第3火曜日、年末年始 |
| 住所: | 仙台市青葉区錦ヶ丘9丁目29-32 |
| TEL: | 022-391-1300 |
| FAX: | 022-391-1301 |
| URL: | http://www.sendai-astro.jp/ |
展示室に展示されている太陽系の模型、各惑星の大きさの比較や距離、日食や月食のしくみ等々、楽しく宇宙の神秘を学ぶことができるとともに、観察会等で夜空の星の観察もできますので、ぜひ、足を運んで下さい。すばらしい星々との出会いがあなたを待っています。
なお、文章内で使用しました写真については、仙台市天文台からご提供頂いたものを使用させて頂きました。どうも、有り難う御座いました。
( 記 : 片桐 眞次 及川 公一郎 )
(記 盟 首 一 酔)
過日 石川県金沢市内を旅行している時、或る、古刹の門前の黒板に白墨で「しみじみと 愚かさを知る 秋彼岸」と書いてありました。何気なく通り過ぎようとしたとき、ハット胸に思い当たるものがありました。
- チラシ等を見て○○スーパーの卵10円安い、納豆が○○円安いと車で遠くまで買に行く 愚かさよ
- 昼食に百円安い、高いと店を替え○万円博打で無くする 愚かさよ
- 交通費を節約するため、高速道路で2時間の場所へ、下道を4時間もかけて行く 愚かさよ
- 太るからと夕飯抜いて、お酒に お肉 お魚 摘みに腹1杯に満足する 愚かさよ
- メタボ 糖尿病 高脂血症と様々な薬のみ 今夜も1杯 元気です。愚かさよ
愚か者 時間だけを もて遊ぶ
編集委員会では、会員の皆様からの原稿を募集しています。
おもしろい話、地域の出来事等、何でも結構ですのでどしどし、お寄せ下さい。まってまーーーす。
【問い合わせ先】
担当:及川 公一郎